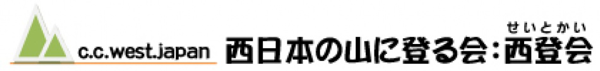2020/3/1 花尾山→帆柱山→権現山→皿倉山

◆メンバー
みいさん、アミちゃん、あっちゃん、おーたさん、オサダさん、わ京子さん ひらの の7人
◆上り776m 下り785m
◆ルート
8:02 登山口出発
9:04 花尾山
9:53 帆柱山
10:37 権現山
11:21 皿倉山
13:46 登山口着

昨日から降り続いた雨で心配していた山行だけど朝には晴れて予定通り8時に出発。すぐに一本だけ咲いている桜を発見🌸今年初のソメイヨシノ?お出迎えありがとう!
気温が上がるとの天気予報だったが風が強く結構寒い。つい足早になるが足元はぐちゃぐちゃの泥。(滑って転んだら泥だらけ⁉️どうしよーと思いつつ)
花尾山→帆柱山→権現山→皿倉山と快調に登り続けお昼はおなじみのビジターセンターにて。
暖かい快適なお部屋にて元気チャージ❢たくさんの人で賑わってた。帰りは行きに出会った桜につがいのメジロが夢中で蜜を吸っている姿にしばらく目を楽しませてもらい本日も怪我無く難なく転ぶことも無く無事に終えた山行でした。皆さまお疲れ様でした!(ひ)
2020年2月8日(土) 皿倉4座縦走

◆ メンバー
おさださん、ひこさん、アミ
◆ ルート
9時00分 煌彩の森コース出発
9時55分 花尾山
10時30分 帆柱山
11時05分 権現山
11時35分 皿倉山
12時00分 ビジターセンターにて昼食
13時20分 煌彩の森コース到着
1月19日に引き続き、本日も皿倉4座を縦走しました。今日はルートを少し変更し、旧ふれあいの森から花尾山へと向かったり、帆柱山へは別ルートを通ったり、権現山へは鷹見神社上宮からのコースを通ったり・・・。様々なバリエーションルートのある皿倉山はまだまだ知らない魅力がありそうです。すっかり皿倉山に魅了されているアミでした。
2019/11/19 秋の開聞岳登山

令和元年11月16日(土曜日)、秋晴の中を鹿児島県指宿市にある開聞岳(924m)の登山を行いました。
今回の特徴は「前日中に鹿児島入りし、朝一番に登山口全員集合」というものでした。仕事のある人は勤務を終えて新幹線に飛び乗り列車内で冷たいビールを楽しんだり、早めに到着した人は黒豚しゃぶしゃぶを堪能したり、指宿の温泉に浸かったりと様々だったようです。まずはこれが楽しかったみたいですね。北九州から鹿児島までは高速道路もつながりました。1時間半で到着する新幹線も開通しました。ホントに便利になったものです。
さて、肝心の登山ですが、朝9時集合、登山を開始しました。今回はグループを脚に自信のある「健脚組」とスロー登山を希望する「マダム組」に分けました。一本道の登山道ならではのやり方でした。
開聞岳は日本百名山のひとつです。特徴は独立峰でほぼ海抜ゼロからスタートすること、薩摩富士と言われる美しい形、そして半島の突端に位置することから遠くの海からでもその姿を確認することができる等が挙げられます。
登山時間は3時間、6合目からは麓の池田湖、錦江湾、さらには遠くに目を凝らすと「あれは屋久島かな…」と見えたような気がしました。澄み切った青空と秋風…記憶に残る素晴らしい山行となりました。
また今回の登山は私(たかちゃん)の700座登頂記念でもありました。会員からフラッグと記念品をプレゼントしていただきました。西登会の皆さんに本当に感謝です。皆さんと一緒だったからここまで頑張って来られました。これからも末永くよろしくお願い致します。
下山後は一人テント泊、車中爆睡、一泊後鹿児島観光、最終便まで焼酎を楽しんだりと…これも様々だったようですが…何はともあれ楽しい秋の開聞岳登山でした。
参加いただいた皆様ご協力ありがとうございました。また参加できなかった方々も応援に感謝です。また行きましょう!文章:たかちゃん(井上)写真提供:アミちゃん
2020/01/19皿倉山・花尾山・帆柱

◆メンバー みいさん、オサダさん、きたさん、アミちゃん
平野 計5人
◆距離(8.4km)登り(671m)下り(747m)
◆行動時間(3h40m)休憩時間(1h17m)合計(4h57m)
◆行程 7:30花尾山登山口出発
7:57花尾山→8:44帆柱山→9:35権現山→10:31皿倉山(昼食)→1:29登山口着
今年に入って遅ればせながら初のお山。前日からの雨で怪しいお天気の中4:30起き、月明かりの中、お墓の隣をすり抜け何ともマニアックな抜け道からあら不思議!バス通り。バスに乗り花尾山登山口。途中小雨で雨具を着たり脱いだりを繰り返しながら花尾山到着。皿倉山のビジターセンターにて昼食。なんとココ!お湯を使っていいらしく、しかもラーメン食べた後の残飯も捨てるザルを流しに設置してあって親切!ありがたや!そしてすぐにストーブ入れてくださり冷えた身体が温まりその気持ちよさに動けなくなる~!皿倉山からはちょうど北九州女子駅伝の撮影隊が陣取っていてこんな所から撮影するのか~!とカメラ機器の発達に驚く。皿倉山からは先ほど登った花尾山が禿げ頭のように見えてチャーミング!その後、黒崎商店街でアップルパイを買ってるんるんと帰宅した平野でした。皆様お疲れ様でした。
2019年12月15日(日) 皿倉山登山(煌彩の森コース→河内貯水池)

◆ メンバー
みいさん・まみちゃん・くみさん・きょうこさん・ひこさん・アミ
◆ ルート
7時30分 皿倉山ケーブルカー駅前出発
【煌彩の森コース】
9時15分 皿倉山山頂
11時00分 河内貯水池下山
12月15日(日)は、みいさん&おさださんの古稀お祝いで皿倉山へ。煌彩の森(直登)コースで山頂へ向かい、河内貯水池へ下山しました。当日は残念ながらおさださんの参加が叶わず、みいさんお一人のみのお祝いをさせていただきましたが、77歳の喜寿の時にはお二人の大好きな久住でぜひとも盛大にお祝いさせてくださいね。今まで怪我やアクシデントもなく日々安全安心登山のみいさん&おさださんの謙虚な姿は私の目標です。そして、西登会は最年長のお二人が一番の健脚です。みいさん、おさださん、いつまでもお元気で私たちを導いてくださいね。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
アミ
2019年10月13日(日) 涌蓋山登山

◆ メンバー
まみちゃん・ひろさん・おさださん・きょうこさん・くみさん・けんちゃん・アミ
◆ ルート
8時15分 公共駐車場出発
8時30分 疥癬湯登山口
10時35分 女岳山頂
10時50分 涌蓋山山頂、昼食
12時10分 湧蓋山山頂出発
13時10分 みそこぶし山
14時20分 一目山、小休止
15時10分 八丁原登山口駐車場
秋晴れの最高のロケーションの中、おさださん号とけんちゃん号にご協力いただき、それぞれの登山口に車をデポして、念願の涌蓋山 ~ みそこぶし山 ~ 一目山を縦走することができました。おさださん、けんちゃん、そして、この素敵なルートをリクエストしてくれたくみさん、ありがとうございます!! 時々強風によろよろとしながらも、目の前に広がるすいこまれそうな程きれいな縦走路にアミは感動が止まりません。そして、みそこぶし山ではまみちゃんのテント講習があり、なるほど納得!と山頂でうなずくメンバー。最後の最後に一目山の手ごわい試練がありましたが、秋の山日和を満喫した涌蓋山登山でした。
2019/09/08.第1回ロープワーク研修
日本山岳会北九州支部様のご厚意により例外的に山岳会の会員以外の団体からの要請で行われた研修会は、初めて行われたにもかかわらず、大きな混乱もなく充実した内容で行われました。台風15号の影響を受けることもなく、午前中は座学と自己確保のためのロープの結束方法を学びました。
昼食休憩をはさんで午後からは、尾倉年長者憩いの家に隣接する広場の傾斜を利用してトラバースから降下と登坂訓練を二人一組で行いました。
暑さも忘れて真剣に取り組む西登会の皆さんを山岳会の指導員の皆さんから学ぶ姿勢が大変良かったとお褒めをいただきました。
三代副会長と相談し、2回目の研修会を打診してみてはどうかと言うことになり、その旨を山岳会へ問い合わせたところ、快諾を得ました。
今後は、2回目のロープワーク研修を行い、岩場などでの上級ロープワーク研修へ移行できればと思っております。
約30名の弱小登山会ではあるものの、会員同士の絆の強さは他の登山会を上回っていると思っておりますが、自己を犠牲にして他人を助けることは美しい行動ですが、それは自己確保という基本的な行動の上に現実化するものです。自己の安全を確保したうえで、全力で助ける行動に素早く移行することができるように日頃からの意識付けと確実なロープワークが必要です。西登会では、登山の際の必携装備にスリング・カナビラを指定していますが、今後は60cmの補助ロープ3本を加えることを推奨しようと思います。今回の研修で学んでほしいことは、安全登山に対する意識付けです。
登山は遊びではあるものの自分の間違った行動のために他人の命を奪う行為になりかねないことを忘れてはいけません。(さ)
2019年8月25日(日)苦行登山塾 第1回 福智山登山

苦行登山塾 第1回目は、福智山 八丁越ルートでの急登登山です。

八丁の急登を登り、さらに福智山山頂への急登を登る女性陣。

福智山山頂に到着!
9時45分に山頂を出発し、黙々と登ってきた道を今度はひたすら下ります。
アミ
2019/8/12〜14白馬岳縦走登山

2019/8/16 河内貯水池ウォーキング(かもく塾)

プレ見学しました。9時30分出発。朝のうちは雨でも降りそうな雲ゆきでしたが、歩いてる間は、一粒も降らずラッキーでした。11時30分スタート地点に到着。ほぼ2時間。その間リーダーが2回もヘビを発見。カワセミにも遭遇。花の名前はあてずっぽでしたが正解だったりする場面もありでちょっと嬉しい。楽しいウォーキングとなりました。お時間ある方は参加されてみてはいかがでしょうか。
本日みた花: マチヨイグサ、コマツナギ、クサギ、ヤマゴボウ、他。鳥: カワセミ、鵜、アオサギ、他
(中)


2019/08/10~2019/08/13 西穂高岳~ジャンダルム~奥穂高岳縦走

初日(8/10)早朝の新幹線で小倉を発ち、名古屋で高山本線に乗り換え、バスで新穂高ロープウェイに着いたのが14時過ぎ。ロープウェイを利用し西穂高口(2156m)まで一気に高度を上げる。そこから西穂山荘まで樹林帯の登山道を進み16時前に受け付けを済ませる。明日の天候を入念に確認し、早々に就寝。
2日目(8/11)2:00amに起床し弁当を食べ3:00amに小屋を出発。夜空には美しい星達が輝いており、昨年と違い好天に期待が膨らむ。西穂独標を経て西穂高(2909m)に5:00am到着。ご来光に手を合わせ山行の無事を祈る。ここからは岩稜帯のアップダウンの続く核心部分となる。身を引き締め下りに入るがすでに十分高度感がある。

P-1直下の急峻な岩場を慎重に下る。赤岩岳付近から間ノ岳(2907m)は浮き石が多く、落石に注意し、手足を使って登る。長い鎖場を過ぎ高度を下げると7:10amに間天のコルに着く。一息入れ緊張をほぐす。逆層スラブを登り天狗の頭を下ると天狗のコルである。8:00着。ここは岳沢小屋へ続く唯一のエスケープルートがある。ここからはジャンダルムまで畳岩尾根の頭、コブ尾根の頭2つのピークを越えねばならない。小屋を出てすでに5時間経過、少しも気が抜ける所が無く緊張、疲労が溜まっている。振り返ってみればこの2つの登りが一番大変だった。このピークを越えジャンダルムが目の前に姿を現した時正直ほっとした。9:40頃。

ジャンダルム(3163m)はザックをデポし身軽になり登頂した。丁度10:00。快晴のなか筆舌に尽くしがたい360度のパノラマの絶景を堪能する。ジャンダルムは信州側からトラバースし通過。次に現れるのがロバの耳。名前は可愛いがとんでもない難所である。高度感のある下りでおまけに足元が全く見えず、足先でフットホールドを探りながら慎重にクライムダウンする。ここを過ぎると最後の難所、馬ノ背が現れる。切り立った垂直の登りは恐怖感すら覚えるが、岩は意外としっかりしておりホールドもあるので3点支持で登りきる。途中からドキドキ感がワクワク感に変わり、自身驚いた。背の部分は細いナイフリッジ状になっており、ここも手足を使いバランスを崩さないように慎重に通過する。

12時過ぎには奥穂高岳(3190m)の頂きに立てた。奥穂高岳山荘に着いた時は極度の緊張から解放され、両大腿部の疲労と相まって虚脱していた。雲海に浮かび上がる山容をぼんやり眺めていると、じわじわ達成感と嬉しさがこみ上げてきて、生涯忘れられない山行となった。実は今回4度目の挑戦でした。いつも天候に左右され途中撤退もありました。体力的にも今年を最後にしようと決めていました。あきらめの悪い私にきっと山の神様も少し微笑んでくれたようですね。
3日目(8/12)は自分の疲労度を考え、涸沢岳、北穂岳の登頂を断念し涸沢、横尾経由で上高地にいたる。
6期 桃野義博
2019/08/11 山岳会企画 風師山縦走

山の日企画は、日本山岳会北九州支部の風師山縦走です。
門司港駅に8時45分集合。西登会から7名の参加です。
台風の風があり、上空には雨雲もあり、意外と涼しいと喜んだ。
海抜0mからかぜかしらまでは、ほぼアスファルトの道路を歩く。すでに汗だく!やはりこの時期の低山は苦行以外の何物でもない。しかも91名の参加者たちがダラダラと歩くのできつい!
かぜがしら山頂では、アイスが配られて大喜び。
一休みすると関門橋や関門海峡へ目をやるゆとりができた。
風師山を経て矢筈山へ歩くが、ここからがまたアップダウンできつい。
やっとの思いでキャンプ場に着いて昼食となりました。
このあと、子供たちがスイカ割りに挑戦。その戦果をいただく。
14時に解散してトボトボと小森江駅まで歩く。駅中の居酒屋風の店で乾杯して労をねぎらう。暑さ厳しき苦しい登山でした。
たかちゃん、まみちゃん、京子さん、畑ママ、ナカジン、あっちゃん、佐々木でした。
2019/8/04 古処山・屏山

◆参加者:長田さん、わ京子さん、アミちゃん、おーたさん、畑ママ、中じん、平野(計7人)
◆行程:屏山(926.6m)⇒古処山(859.5m)縦走
7:00am 嘉麻市 遊人の杜キャンプ場より出発。「屋外での不要な運動・作業は命の危険もあるのでお控えください」という毎日のニュースの中、立山で思い切り高山病になった筆者は無事に下山まで身が持ちこたえるだろうかという不安に苛まれながらの参加であった。ところがキャンプ場(518m)はすでにひんやりと明らかに下界と違う空気の冷たさ。まずは快調に歩き始めるがすぐに急登が現れる。三点確保しつつも、両手両足使っての鎖場の山登りらしい山登りは久しぶりで高度をグングン稼ぎ何だか楽しい。太陽にさえぎられる林道は直射日光が届かないので涼しさが続く。休憩を取りつつも9:22am屏山到着。途中、奥の院という岩の切れ目から冷気が陽に透かして上がって来るのが見えたので自然のクーラーとばかりにしばし顔を突っ込みリフレッシュする。10:31am 古処山到着。それまで登山者に会わなかったのにここはたくさんの登山者で賑わっていた。昼食を取りキツネノカミソリ(オレンジ色)と銀梅草(白)にも会え(フォトギャラリー掲載)たが、見晴らしはいまいちだった。12:43登山口に戻る。今回初めてYAMAPというアプリを家でDLしてきて使ってみたが、歩いた軌跡、時間、距離など記録され山行記録を書くにあたり大変便利だった。夏山は700m以上!というアミちゃんの言葉を体感して納得した筆者であった。皆様、お疲れ様でした。行かれなかった皆様、近くにある涼しい山、次回ご一緒しませんか?(ひ)
2019年7月13日(土)〜7月15日(祝月) 立山遠征

🔸参加者🔸
あみちゃん・ひろちゃん・くみさん・あっちゃん・なかじー・とみさん・いくみ の計7名
🔸行程🔸
7/13 朝6:10発の新幹線のぞみ2号に乗り、京都からサンダーバード、金沢から北陸新幹線”はくたか”でJR富山駅へ。電鉄富山、立山ケーブルカー、立山高原バスと乗り換えてやっと立山室堂に到着したのが15:30。そこから立山室堂山荘まで徒歩で20分。
コロコロのスーツケースを持って行ってしまい、室堂からの徒歩移動で泣きを見てしまった。立山室堂山荘に泊まられる方はザックとサブバッグに収まる程度の荷物の量にしましょう。(反省1)
行き帰り一日ずつは移動日となるので、
山は7/14の実質一日だけ。立山三山登山予定でしたが、あいにくの雨😭
7:35 室堂山荘出発
8:55 一の越到着・休憩
10:36 立山雄山登頂・
雄山山頂神社でお祓い⛩・昼食
12:08 雄山出発
14:00 室堂山荘到着
まあ、雄山登山だけの単純な山行時間の記録だとこれだけなのだが・・・
この一座を無事におりてくるだけでもたくさんのドラマが繰り広げられた。
何しろ☔️雨☔️。
前日の夜、ガイドさんから「天気予報によると一日中雨です。」と、縦走どころか、視界も景色も、いや登山そのものも望めない可能性がある事を告げられ、皆半分以上は諦めていた。
が、一縷の望みが叶い雨も小雨に!皆の体調も確認してガイドさんのゴーサインによって7:30出発となる。
2,500m以上級の山で怖いのが「高山病」。経験のない高山でこの酔いの症状が出るか出ないかは行ってみないとわからない。
という中で、案の定2名ほど「頭痛・吐気・嘔吐・気分不良」などの低酸素状態に陥っていつもの元気が出なかった者もいた。
が、定期的に血中濃度測定(パルスオキシメーター)をしたり、頭痛薬、吐き気どめなどの薬を駆使してなんとか雄山に向けて歩く出す事にした。
冬は雪が少なかったそうだが、春頃何度か降雪したせいか、雪渓を渡る箇所が数箇所あった。
皆アイゼンを持参はしていたが、キックステップで歩く練習をする。登りはいいが、下りで踵からグッと雪に埋め込み進む要領が難しく、転倒回避できなかったメンバーも数人いたが、雪の上は痛くないのでちょっと楽しそうだった。
そんなこんなで歩くのに結構時間がかかり、一の越から雄山神社に到着する際、後続隊に何度も道を譲ってしまった。大汝山くらいまでなら行けるかもと思っていたが、ちょうど雨も本降りになってきて、足元も滑って危険な箇所があるとの事で、雄山登頂だけで勇気の撤退となる。西登会で基本的な技術の練習を仕込まれていた事が功を奏して、皆怪我する事なく無事に下山できたが、悪天候や高山対策など訓練の積み重ねが必要である事を実感した。(反省2)
しかし、比較的お天気は味方してくれて、行動時は小雨、雄山神社でお祓いを受ける時間は奇跡的に一粒も降る事なかった。次のグループは大雨で外でのお祓い中止となっていたので本当にラッキーだったと思う。
軽い高山酔いになったメンバーも、高度を下げるにつれて元気を取り戻しいつものおしゃべりに花を咲かせることができていたので安堵した。
最終日、7/15の朝、室堂ターミナルを綺麗に覆う様に虹が架かり🌈素晴らしい景色も見ることができて、大満足の立山遠征となった事を報告する。(も)
2019年6月23日(日) 由布岳東峰登山

◆ メンバー
くみさん・なかじん・畑ママ・あっちゃん・アミ
◆ ルート
7時00分 由布岳正面登山口 出発 ➡ 8時00分 合野越 ➡ 10時15分 マタエ分岐、小休止 ➡ 11時20分 由布岳東峰山頂 到着 ➡ 14時15分 由布岳正面登山口 到着
6時30分頃に駐車場へ到着。無料駐車場はすでに10台程の車があった。一枚羽織りたくなるくらいの寒さだったが、アブや虫たちはすでに活動を開始していて、虫除けスプレーをふりつつ歩みを進めた。快晴のおかげで、つづら折りの道から時折 由布院の街並みを眺めることができた。今まで何度か由布岳を訪れたが、これほど綺麗な景色を眺めたのは今回が初めてだった。ガレ場を登り詰めて、西峰と東峰の分岐であるマタエに到着。昨年はガスで西峰の姿すら全く見えなかったが、今日は鎖場を登って西峰へ向かう登山者の姿まで はっきりと見える程 お天気に恵まれ、また風も微風だった。マタエで小休止後、東峰へ。山頂は人が少なく、ここでまた小休止。のんびりと山頂を堪能して、14時15分頃 無事に下山。
梅雨入り前の貴重な晴れ間に、運良く由布岳に登ることが出来た今回の山旅でした。(あ)
2019/6/16 登山教室 平尾台最高峰貫山

6回シリーズで行われた登山教室の最終回は、貫山⇒偽水晶山⇒水晶山の三座を縦走しました。写真は水晶山です。最終回なので約12km歩きました。今回の受講生は4名でしたが、3名が入会しました。
★ひこさん
★きたさん
★みちさん
今後は11期生を暖かくお迎えください。
歓迎登山は湯川山に決定しました。(さ)
2019/6/9 登山教室 目白洞ケービング

日差しの強い台上を後にして、目白洞でケービングです。郷のガイドに連れられて10人ほどが先に入洞しました。本日の我々の目的地はベーコン岩です。先日の雨と10人ほどが先に歩いていることもあって、洞内はヌルヌル滑って歩きにくい。四名の受講生は初めてのケービングで別世界を体験しハイテンションになっていました。私も初めての入洞の時は興奮したものでした。真新しいツナギ服が泥だらけになってはしゃいでいたした。洞窟を作るための長い時間を天井や壁に見ることができます。こんな時に、自然の雄大さや人間の小ささを知るのですね。
そろそろ卒業が近づいてきた11期生。これからどんな山でどんな人生を重ねるのでしょうね?11期の受講生が西登会で人間的にも技術的にも成長してくれたら、こんなうれしいことはありません。諸先輩たちの暖かく厳しい応援をよろしくお願いします。次回は最終回の貫山です。
貫山→偽水晶→水晶山の予定です。(さ)
2019年6月9日(日) 久住山・扇ヶ鼻登山

◆ メンバー
まみちゃん・ひろさん・いくちゃん・ももちゃん・くみさん・はたちゃん・なかじん・あっちゃん・とみちゃん・アミ
◆ ルート
7時45分 牧ノ戸駐車場 出発 ➡ 10時00分 星生山分岐(西千里浜) ➡ 10時55分 久住山・中岳分岐 ➡ 11時35分 久住山山頂 到着、昼食 ➡ 12時15分 久住山山頂 出発 ➡ 12時40分 久住別れ、トイレ休憩 ➡ 13時20分 星生山分岐(西千里浜)➡ 13時55分 扇ヶ鼻山頂 到着、小休止 ➡ 15時10分 牧ノ戸駐車場 到着
今年も九重のミヤマキリシマの季節がやって来ました!
7時10分頃に牧ノ戸駐車場に到着。駐車場はすでに大勢の登山者で賑わっていて、沓掛山手前の岩場は大渋滞。それもそのはず、楽しみにしていたミヤマキリシマの花はちょうど見頃を迎えていて、あたり一面、どこを見渡しても、九重の山々はミヤマキリシマでいっぱいだった。
だが、久住別れに着く頃にはガスが立ち込めてしまい、まわりが全く見えなくなってしまった。ガスが晴れた頃を見計らい、久住山へと向かう。山肌がミヤマキリシマ色に染まっているせいか、いつもの雄々しい久住山とは違って見えた。運良く、久住山山頂の特等席が空いていたので、九重の山々を眺めながらの昼食に。
久住山下山後はミヤマキリシマに誘われるように扇ヶ鼻へと向かう。分岐から扇ヶ鼻への15分間は急登できつかったイメージしかなかったのだが、今回 イメージがガラリと変わった。15分間の道のりに咲いているミヤマキリシマの美しいこと! 思わず扇ヶ鼻山頂で小休止に。写真を撮影したり、お昼寝をしたりとのんびり過ごす。最後まで気を引き締め、15時10分 無事下山。
新たな九重の山々の魅力を知った久住山・扇ヶ鼻登山でした。(あ)

扇ヶ鼻山頂へ向かう途中にて。山頂近辺はミヤマキリシマのお花畑が広がっていました。
2019/6/2 平尾台自然の郷11期生 登山教室

今回は、苅田町との境界にある尾根を歩きました。堂金山⇒不動山⇒
風神山⇒大かんの台の4座を歩きました。山を楽しみながら歩くことを少しづつ感じている受講生でした。本日の応援者は、まみちゃんと畑ママでした。感謝です。(さ)
2019/5/26平尾台自然の郷11期生 登山教室

登山日和ではあるものの気温が高く熱中症に気を付けながらの登山となりました。本日のルートは、茶ケ床に車を止めてアスファルトを中峠に向けて歩き権現山の直登ルートへ進入。喘ぎながら山頂に立つ(写真)
いきなりハードだったかな?受講生も支援者もバテてました。その後周防台に登頂し尾根を下って広谷へ、途中佐々木と合流する。小さな広谷湿原を俯瞰する。目を上げると鬼の唐手岩がニョキット立っている。この岩が出現するときに立ち会ったとしたら、この平尾台はグラグラと揺れて火の海だったのだろか?その唐手岩の付け根にある滝が本日の昼食場所です。広谷湿原から流れ出る水が花崗岩の段差で小さな滝となる場所で不動滝と呼ばれています。この辺りでは青龍窟とここだけが日陰となります。昼食をとりながら日頃身に着いた邪悪を取り除ければ一石二鳥です。今日も有意義な山歩きを楽しみました。同行する仲間との絆は登山回数に比例して増していきますが、そうした通い合う気持ちがとても爽快な平尾台の景色とマッチして「今日も生きててよかったなーー」と思う瞬間でもありました。一日を引っ張っていただいた井上SLにも感謝です。(さ)
2019年4月28日(日)~ 5月1日(祝水) 屋久島遠征

白谷雲水峡 太鼓岩にて。 太鼓岩に到着した時、奇跡的に雨が止みました!!



大粒の雨の中、清涼橋(つり橋)にて。
2019/4/28 竜王山(飯塚)615m

2019年4月14日(日) 足立山 ➡ 戸ノ上山 登山




◆ ルート
6時30分 JR安部山公園駅 出発 ➡ 7時05分登山口(4番カーブ)➡ 7時55分 砲台山 ➡ 8時30分 足立山 ➡ 10時15分 吉志分岐 ➡ 10時35分 畑貯水池分岐 ➡ 11時00分 大台ヶ原 ➡ 11時30分 戸ノ上山、昼食 ➡ 12時40分 寺内・大久保の分岐 ➡ 12時50分 大久保バス停登山口
◆ メンバー
みいさん・ヒロさん・いくちゃん・アミ
今日の足立山から戸ノ上山への道のりは、鳥のさえずりを聞きながら、また時には色とりどりの花々を楽しみながらの登山になった。途中、イノシシが道を掘り返した跡があまりにも多くて、小さな物音にビクビクしながら歩く場面もあったが、大台ヶ原では心地よい風が吹き、季節はすっかり春を迎えていた。大台ヶ原を過ぎてすぐの急登は相変わらずきつかったが、菫や鈴蘭水仙の春の花々に出会えた。
戸ノ上山山頂は気温が何と22℃もあった。どうりで暑いはず。ただ、じっとしているとすぐに寒くなるので、今日もこまめに衣服調整。
昼食後に出発しようとすると空が急に暗くなり、戸ノ上山を下山中の12時20分頃には予定より早く雨が降り出した。樹林帯の「自然の傘」のおかげで、新緑を弾む雨音を聞きながら、しばらくは雨具を着けずに進んだ。寺内・大久保の分岐手前で雨具とザックカバーを装着。みいさんの冷静な判断で、下山は予定していた寺内ではなく大久保を選択。雨で滑りやすい足元に注意しながら、ロープにしがみつきながらの下山になったが、寺内よりも早く下山することができ、冷たい雨にあまり体を冷やさずに済んだ。先月の尺岳登山でのルート間違いの時にも思いましたが、今日も改めて「前もって地図を見よう」と反省した足立山・戸ノ上山登山でした。(あ)
2019/4/7 皿倉山(登り国見岩、下り煌彩の森)コース

🔷メンバー 網ちゃん、あっちゃん、マミちゃん、わ京子さん、松谷夫妻、平野
2019年3月31日(日) 牛斬山 ➡ 福智山 ➡ 尺岳 ➡ 皿倉山縦走

◆ ルート
[ JR城野駅よりタクシーにてJR採銅所駅へ移動 ]
7時 JR採銅所駅 出発(標高90m)➡ 8時16分 牛斬山(580m)➡ 8時52分 山犬の峠(625.1m)➡ 9時22分 焼立山(759m)➡ 9時40分 赤牟田の辻(791m)➡ 10時30分 頂吉分岐 ➡ 11時02分 福智山(900.6m)➡ 荒宿荘にて昼食 ➡ 11時50分 烏落とし ➡ 12時10分 豊前越 ➡ 12時40分 山瀬越 ➡ 13時10分 尺岳(608m)➡ 14時10分 田代別れ ➡ 14時41分 観音越 ➡ 16時30分 市の瀬峠 ➡ 17時50分 皿倉山ケーブルカー駅 ➡ ケーブルカーにて下山
◆ メンバー
みいさん・ももちゃん・おさださん・アミ・福智山からヒロさん合流
出発地点のJR採銅所駅の周辺は、桜の花が満開だった。今日の天気予報は、寒の戻り+強風予報。特に福智山までの道のりは、時折 粉雪がチラチラと舞うような寒さに。体を冷やさない様、こまめに衣服調整しながらの登山となった。
ちょうどこの日は、ある山岳会が牛斬山➡皿倉山のトレイルランを開催していて、ランナーの下りでの驚異的な速さを間近で見ることができた。また、牛斬山からのアップダウンの繰り返しに、先行きが心配になるほど疲れていたのだが、ランナー達の元気いっぱいに走る姿を見ていると、何だかこちらまで足取りが軽くなり、苦しいながらも頑張れる前半戦になった。
福智山山頂は、強風予報通り、いても立っていられない程の風が吹き荒れていた。そして、山頂の温度計は2℃。お参り後、一目散に山頂を下り荒宿荘へ向かっていると、途中で上野峡から登って来たヒロさんと合流。荒宿荘の前で昼食をとり、次に目指す山、尺岳へと向かった。
福智山から皿倉山までの後半戦のルートは、樹林帯の中をただひたすらに黙々とアップダウンを繰り返しながら歩いた。観音越からは2つの山を巻きながら市の瀬峠へ向かうのだか、幅が細くてやや斜めの道が、疲れのせいか、晴天続きの影響か、トレイルランの後からか、先週よりも滑りやすいように感じた。もし日が暮れた後だったら、私の技術ではヘッドランプの光を頼りにこの道を歩くことは厳しいだろうなと思った。また、登山道を塞ぐ倒木はくぐって通ったりした(先週、脇道に逸れると合流が大変だった為)。今回は例年より1時間早く出発したのだか、陽があることの安心感は計り知れないものがあった。31日は18時30分に日没だったが、17時50分には皿倉山ケーブルカー駅に到着。今年もみんなで無事に完歩することが出来ました。
これもひとえに、みいさんの入念な山行計画と、疲労が蓄積されている状況でも常に一定のペースでみんなを引っ張ってくたおかげです。みんなを代表して、みいさん、今回もお世話になりました。ありがとうございました!(あ)
2019年3月24日(日) 尺岳 ➡ 皿倉山プチ縦走

◆ ルート
[ JR石原町駅よりタクシーにて菅生の滝へ移動 ]
8時 菅生の滝駐車場 出発 ➡ 8時35分 尺岳登山口 ➡ 1時間ロス ➡ 10時55分 尺岳(608m),昼食 ➡ 12時20分 田代別れ ➡ 13時00分 観音越 ➡ 15時00分 市の瀬峠 ➡ 16時50分 皿倉山ケーブルカー駅 ➡ ケーブルカーにて下山
◆ メンバー
ヒロさん・きょうこさん・アミ
[菅生の滝]の手前を左に曲がり、急登へ。這うように登りつめると、林道に出た。暫く林道を歩き、登山口からは沢沿いをまっすぐに進む...、のはずが、事前のルート確認不足のために、沢沿いで途中の道を左に曲がってしまい、1時間のロス発生。ヒロさんのYAMAP地図のおかげで無事に本ルートへと戻り、気持ちを切り替えて尺岳山頂へ。ちょっと早いが山頂で昼食を食べ、予定通り皿倉山へと向かう。疲れた体に登りは辛く、木の登り階段が恨めしい。一人だときっと気持ちが折れてしまうのだが、今日はヒロさん、きょうこさんと一緒なので心強く、一歩一歩 確実に歩き、何とか皿倉山ケーブルカー駅に到着することが出来た。一生懸命頑張ったご褒美だろうか、あたり一面に広がる雲一つない澄んだ青空が、とてもきれいだった。
来週の本番も頑張ります!(あ)
2019/3/17(日)皿倉山(国見岩コース)

メンバー[網ちゃん、長田さん、あっちゃん、わ京子さん、三代さん、マミちゃん、平野の7人]


2019/2/24在自山

【2019/2/24(日) 在自山 山行】

【在自(あらじ)山 山行記録】
2018年9月23日(祝日) 津波土山(大分県)登山

◆ メンバー
momo,kentaro,ami
◆ ルート
9時25分 駐車場出発 ➡ 9時35分 登山口 ➡ 西岩尾根 ➡ 12時~12時35分 津波土山山頂(昼食)➡ 東岩尾根 ➡ 登山口 ➡ 14時30分 駐車場到着
前々日の雨の影響がまだ残っていて、登山道は土が湿っていた。岩場は乾いていることを祈りながら谷間を進む。西岩尾根への岩をよじ登ると、無明橋に到着。曇りだが、目の前に鶴見&由布岳の姿がはっきりと見え、今日もまた絶景だ。
景色を楽しみ、先へ進むが、日の当たらない岩場は表面がまた湿っていて、やはり滑る。苔が生えている岩は、また更に滑りやすくなっていた。三点確保、体重移動にいつも以上に神経を張り巡らせ、「針の耳」や様々なトラバース箇所を通過。
尾根に出ては谷間に急降下するを繰り返し、谷間 ⇔ 山頂間のガレ場に到着。足元の悪いこのガレ場をピストンするのかと思うと逃げたくなる。逃げ場はないが ...。ズルズル滑りながらガレ場を登り、山頂に到着。
昼食後、momo&kentaroに待ってもらいながら、時には四つん這いになりながら、長いガレ場の坂を下る。
途中、弘法大師像に手を合わせ、東岩尾根の取付の分岐に出る。木の根っこに滑りながら斜面をよじ登り、岩場をトラバースして東岩尾根へ。
東岩尾根も眺望が良く、切り立った岩肌や午前中に通ったルートを眺めながら、しばし休憩。ラストの88番の大師像に手を合わせ、鎖のある長い急斜面を下り、無事に駐車場に到着。
登山時間 約5時間の、岩山をお腹いっぱい堪能した、津波土山登山でした。(あ)
2018/8/31~9/4 はっちゃん(7期)の裏銀座縦走記

行動日: 2018年 8月31日〜9月4日
場所: 裏銀座(北アルプス)長野県・岐阜県・富山県
1日目(8/31)行動時間1時半
新穂高温泉登山口(1090㍍)〜わさび平小屋(1360㍍)(泊)
2日目(9/1)行動時間7時間
わさび平小屋~鏡池~双六小屋(2550㍍)(泊)
3日目(9/2)行動時間11時間
双六小屋~双六岳(2860㍍)
~三俣蓮華岳(2841㍍)~鷲羽岳(2924㍍)~水晶岳(2986㍍)〜水晶小屋(2880㍍)
4日目(9/3)行動時間12時間半
水晶小屋~わさび平小屋(泊)
5日目(9/4)行動時間1時間半
わさび平小屋~新穂高温泉登山口
今回の裏銀座縦走の起点は、岐阜県側の北アルプスの玄関口である新穂高温泉です。
双六岳~三俣蓮華岳~鷲羽岳~水晶岳~野口五郎岳~烏帽子岳を4泊5日で縦走し、ブナ立尾根を高瀬ダムへと下山する予定でしたが、台風接近のため、野口五郎岳・烏帽子岳は登頂できず、水晶小屋~わさび平小屋のピストンとなりました。
裏銀座縦走路は、表銀座縦走路と立山~薬師岳の稜線に挟まれ、下界がまったく見えません。
標高2900㍍以上の山に囲まれ、森林限界より下は1度も下らない北アルプスの深さと高さとが感じられ、登山者の少ない縦走コースです。

①前半は雨とガスの為雨具を着けての行動となり、鏡池に映る槍ヶ岳や、双六岳までの縦走路での常念岳や大天井岳、穂高連峰、槍ヶ岳の絶景も見ることができず、ただひたすら水晶岳をめざしアップダウンの縦走路を歩く「我慢」の山行となりました。
三俣山荘に到着した頃には雨も止み、鷲が羽を広げた山容の鷲ヶ岳が目の前にありました。その鷲ヶ岳をジグザグに登り2時間程で水晶小屋に到着。「黒部湖」を眼下に、野口五郎岳・烏帽子岳などが出迎えてくれました。水晶小屋は深い山奥の小さな山小屋です。ザックをデポして水晶岳山頂をめざしました。北アルプスのど真ん中、百名山の中でも最も奥深い水晶岳、どこから登っても2日はかかる山です。山頂ではガスの切れ間から白馬岳・後立山連峰・剣岳・立山連峰
・薬師岳・黒部五郎岳など昨年から恋焦がれていた黒部源流の山々がその山容を見せてくれました。
「よーやく会えた山々」に「ありがとう」としか言えませんでした。
②後半は台風接近の為予定変更して、水晶小屋からわさび平小屋まで戻ります。
2日かけて登ってきた縦走路を1日で下ります。
水晶小屋を朝5:00出発。黒部川源流の登山路をたどり再度三俣蓮華岳山頂へ、西穂高岳・ジャンダルム・奥穂高岳・北穂高岳・大キレット・南岳・槍ヶ岳・北鎌尾根などの穂高連峰、燕岳・常念岳・大天井岳などの表銀座の稜線が平行して見える双六岳の巻道を一気にくだりました。
わさび平小屋に到着したのは17:30頃でした。どうにか山中での台風との遭遇はまぬがれました。
最終日はわさび平小屋から新穂高温泉登山口までの1時間半の林道歩きでした。
今回登頂を断念した、烏帽子岳と野口五郎岳は、来年の宿題として、今回と違うコースで挑戦したいと思います。
そろそろ山は秋の花にかわっています。群生するチングルマの髭に、オオヒョウタンボクとナナカマドの真っ赤な実に癒され、イワギキョウやウサギキクの可憐な姿に励まされながらの山行でした。
2018 9.9 古谷(7期)
2018/8/5~郁ちゃん(5期生)の四姑娘山 フラワーウォッチングの旅

「四姑娘山」の南東にある4500m級の「巴郎山(はろうさん)」山麓には、ヤクが放牧されている広大な草原がある。
標高3500m~4000mの高山でしか見られないイブキトラノオやエーデルワイス・ブルーポピーなどの様々な高山植物を期待しての参加である。
そこで日本では滅多にお目にかかれないブルーポピーと早速遭遇できた。



道端の上の方のお花の写真を撮り、足元の可愛らしい高山植物を愛で、としているうちにやはりなんだか頭がクラクラしてくる。これが酸素不足の症状か?
慌ててもらった携帯酸素を口元に当てて吸い込むと少し楽になった。この後、すわ高山病か?と苦しむ一夜を過ごしたが無事に回復。そして、いきなり最終日の絶景。


2018年8月11日 由布岳 東峰登山

◇ ルート :正面登山道
◇ メンバー:角さん、ケンタローさん、アミちゃん、おーたさん、
なかじん、平野 6名
5:00 北九州市立文化記念公園に集合
7:00 駐車場出発
7:50 合野超到着
9:20 マタエ到着
9:55 東峰山頂到着
12:45 下山
お盆休みの初日でもあり、懸念していた交通状況はいつもより多少車が多いもののスムーズに流れ、行きも帰りも予定していた時間内に到着した。お天気は途中ガスってきたが、雨具を出す必要もなかった。
下界の暑さに比べさすがに山はひんやりと涼しい。
今年のこの酷暑の中で、あり得ないと思った由布岳登山だったが、
早朝出発で渋滞と、暑さは緩和されたものの、利尻以来の登山で体力に大きな不安もあったが何とか登れた(感想には個人差があります)
下山後、湯布院散策を楽しむメンバーだった。皆様、お疲れ様でした。
2018年7月14日 利尻登山 山行記録

その① 利尻山とは・・・
日本最北地の北海道 稚内から約20㎞海を渡ると、利尻島、礼文島という島々があります。
その利尻島のほぼ真ん中にそびえ立つのが、日本百名山の「利尻山」です。
利尻山には山頂が2峰あるのですが、最高峰の南峰(1721m)は崩落が進み危険で立入禁止となって いる為、一般的には北峰(1719m)が利尻山山頂と呼ばれています。
利尻山は自然豊かな山で、「花の百名山」にも選ばれている花の宝庫な山です。 また、渡り鳥の中継地としても知られています。
水も豊かで、鴛泊コースの3合目付近には 「甘露泉水(かんろせんすい)」と呼ばれる、ミネラルたっぷりの味わいまろやかな湧水がこんこんと 湧き出ています。
そんな自然豊かな利尻山へおーたさん、くみさん、なかじん、アミタの4人+ガイドの渡辺さん+関西から来られたお2人の合計7人で行ってきました。(写真;八合目の先から見た利尻山)その②に続く

その②
◇ ルート:鴛泊コースピストン ◇ 登山時間:休憩含め12時間
04:20am 2合目(220m) 北麓野営場 出発 3~5合目くらいまでは、登山道の両側に「ウルシ」が びっしりと茂っている要注意箇所が多々あり。 ガイドさんからの「ウルシ注意報」がなければ、 登山道の道幅が狭いので何かの拍子に触ってしまっていたかも。
04:35am 3合目(270m) 甘露泉水 北麓野営場からすぐに甘露泉水に到着。水場はここのみ。 水温が平均5.5℃と真から冷えていて、 下山後のクールダウンにピッタリ。
05:15am 4合目(390m) 道標「野鳥の森」 森の森林浴と、近くから聞こえる「駒鳥」(こまどり)の 澄んだ声が心地よい。「駒鳥」は、さえずりが馬の嘶きの ように聞こえることが名前の由来との事。
05:55am 5合目(610m) 道標「雷鳥の道標」 明治時代、この付近で雷鳥が現れて道を先導したことが名前の由来との事。残念ながら、利尻山には雷鳥は生息していないらしい。
(写真;雪渓とお花畑)その③に続く

その③
06:25am 6合目(760m) 第一見晴台。その名の通り、あたり一面見晴らしが良く、正面にはこれから目指す長官山、 後ろには雲海から顔をのぞかせた礼文岳(礼文島)の姿が 見えた。しばらくするとガスが出てきてしまい、絶景はおあずけに。
06:55am 7合目(895m) 道標「胸突き八丁」 前半の難所である「胸突き八丁」。 道はジグザグでゴロゴロ岩の多い急登。 雪の重みに耐えかねた木の幹が 横に伸びていて、ますます歩きにくい。 ガイドさんの「あと5分で第二見晴台ですよ」という言葉を聞いて、疲れた気持ちをリセットし、 残りの力を振り絞って急登を駆け上がる。
07:30am 7.5合目(1120m) 第二見晴台。岩のテラスに腰を下ろし、小休止。 依然、ガスは取れず。絶景は見れないものの、 イワギキョウの可憐な姿に疲れが癒される。
08:00am 8合目(1218.4m) 長官山 ここから利尻山の姿が見えるはずだが、 あいにくのガスで全く見えず。 泣く泣く緩やかな下り坂を歩いていると 「エゾシマリス」に遭遇。しっぽまで縞々で可愛い。 するとだんだんとガスが晴れ、少しずつ利尻山の姿が見えてくる。みんなから歓声が上がる。 山にはまだ雪渓が残っている。決して標高の高い山ではないのに、利尻山の放つ迫力はすごい。
(写真;イワギキョウ)その④に続く

その④
08:15am 避難小屋(1230m) トイレブースが2個あり。他は、6.5合目と9合目に それぞれ1個ずつトイレブースが設置されていた。
09:00am 9合目(1410m) 道標「ここからが正念場!」 ここから山頂までの標高差は約300m。 そして足元が火山礫になり、足に力を入れると崩れて滑る。 横の山壁は、触るとポロポロと取れる。 今までにない道に悪戦苦闘するも、誰一人 弱音をはく人はいない。お花畑や、青空と海原の美しさにたくさんの元気をもらう。 一歩ずつ足を前に出しているといつの間にか山頂へ。
10:10am 利尻山山頂(1719m)到着! この瞬間を夢見て、みんなで一緒に頑張ってきた。 みんなで一緒に山頂に立つことができて 本当に嬉しかったです。 おーたさん、くみさん、なかじん、ありがとうございました!
(写真;山頂に立つ4人)その⑤に続く

その⑤
10:50am 下山開始。もともと下山の苦手なアミタなのに、 火山礫の道を下りるだなんて(涙)。 超へっぴり腰で下りていると、 後ろからまるでスキーのような華麗な滑りで くみさんが軽やかに下りてきました。 ガイドさんも「火山礫を利用して滑りながら下りてきたらいいですよ」との事。が、高度な技術を真似できず、 超へっぴり腰のまま9合目まで下山。
11:50am 9合目青空のもと、礼文島や樺太が 綺麗に見えた。
リシリヒナゲシにも会えた。 青空のおかげで眺望は最高なもの、暑い! 利尻山は空気が澄んでいて緯度が高いので、 太陽の日差しをモロに受けるとか。 下山は途中6合目まで暑さとの戦いとなった。
12:50pm 8合目、暑さの為、利尻山に感謝を告げ、早々に出発。 14:10pm 6合目 第一見晴台 樹林帯に入り、やっと暑さから解放される。 登山靴を脱いでクールダウン。 利尻空港を離陸した飛行機を見送り、 私たちも出発。
16:20pm 2合目 到着。無事に下山。
<後記> 2年越しに登頂することが出来た利尻山。 色んな思いがあり、今回登山記録を書かせて もらいました。キツい箇所も多々ありましたが、 やはり一番記憶に残っているのは みんなとの楽しい思い出ばかりです。 くみさんと一緒に「よっこいしょ、どっこいしょ」と 声を出しながら登った急登。 9合目からのおーたさんのガッツ。 キツい時でも明るい なかじんの笑顔。 今回もたくさんの感動、思い出深い楽しい4日間を ありがとうございました。 (写真;利尻山から見た礼文島) 2018/7/20 アミタ
2018年5月4日(祝金) 屋久島 宮之浦岳登山

憧れの屋久島 宮之浦岳へ
おーたさん、いくちゃん、ももちゃん、
初ちゃん、京子さん、アミタ
の6名で行ってきました。
雨を覚悟していたものの、
私たちが滞在していた3日~6日は
雨に逢うことは無く、風は強かったですが、
お天気にも恵まれ、
良い仲間と良いガイドさんに恵まれ、
最高のGW登山をすることができました。
今回は、
淀川登山口から宮之浦岳のピストンで、
登山時間13時間の超長丁場コースでしたが、
みんなで一緒に山頂に立つことができて、
本当に嬉しかったです。
写真を見ると、
いまだにあの感動が蘇ってきます(^-^)。
ありがとうございました!
1月21日(日) 干支登山 荒滝山/山口県宇部市
干支登山は、県内にある犬ケ岳と犬鳴山が遭難者があって縁起が良くないという理由で却下されました。近場で犬に関係する山は無く、年末年始を干支登山の山探しに費やすこととなりました。年が明けて、何気なくヤマレコを見ていると、山口県に犬ケ迫登山口から入山する荒滝山を発見しました。荒滝山に関するホームページもあり、地元の関係者が保全活動等を行い登山道は整備されているようです。
したがって、この山に決定!!と言うわけで10名の参加で山口県宇部市の荒滝山の犬ケ迫登山口から日ノ岳を経由して荒滝山を目指します。しかし、里山と言うのは難しいですね。通常のルートは荒滝山へ向かう登山道で案内看板が設置されています。私たちは逆ルートなので看板などの案内がありません。25000の地図で日ノ岳に向かうルートを探しました。あちらこちらに道があってここで一番時間を費やしてしまいました。地元の農家の方に偶然会ったので登山口を訪ねてやっとルートを発見し登山開始です。あまり人が入っていないようで登山道は荒れています。低山のわりに急登が長く続きます。このあたりから気合を入れなおさないと気が付きました。古い山城の跡で町の史跡になっているようです。吹く風が冷たく体がなかなか温まりません。昼食前に日ノ岳に登頂。山頂から荒滝山が望めます。小さな富士山のようです。記念写真を写し終え登山道を荒滝山に向けて進みます。途中12時の時報のサイレンが遠くに聞こえたので樹林帯の中で昼食となりました。
荒滝山の山頂は山城があったことを思わせる地形で展望が良く遠くに鶴見岳を望むことができました。本日のメインイベントは、犬に関連するグッズを身に着けて記念写真に納まることです。笑顔と歓声に包まれながら無事に干支登山の荒滝山山頂から連なる山々を満足な気分で眺め、今年一年の安全登山を祈念しました。
1月7日(日) 初詣登山 英彦山
まみちゃんからのお誘いで急きょ初詣登山で英彦山中岳と南岳に行ってきました。期待したほどの雪は無く、正面登山口の不規則な石段を息を切らせて登りました。これも修行だし参拝の儀式とあきらめて中宮を目指します。途中、修験者の一団がほら貝を鳴らしながら登ってきました。厳かな雰囲気が中宮を包みました。中岳の8号目あたり、結び神社付近から雪が登山道を覆うって来るようになりました。10年ほど前は、うっそうとしていた9合目当たりの登山道は台風や温暖化?の影響か大木の杉がすっかり見ることができなくなりました。奉幣殿も老朽化が進行し傾いています。唯一進化したのは、山頂の休憩所にバイオトイレが稼働していることです。今日も担当の登山会の方がメンテナンスに来られていました。「お疲れ様です」。運よく休憩所のテーブルが空いたので、まみちゃん特性のお汁粉を持参のコンロで作って、おもちも焼いて、おいしくいただきました。その後南岳を巻いて鬼杉から登ってくるルートに合流し、南岳に登頂しました。アイゼンを着けたり外したりしながら北西尾根を下りバードラインに合流して、車を一台停めていた県立青年の家に下山し、なごみの湯でお湯をいただきました。お腹が空いたので田川山賊鍋で夕食としました。満足な初詣登山でした。
12月17日 九州百名山 鹿嵐山周回登山
小雪が舞う寒い朝となりました。大分自動車道を南下し宇佐インターチェンジを降りて、登山口を目指します。大きな駐車場が第一・第二ともあり、それぞれに一台ずつ車を止めました。耶馬渓の荒々しい山容が見どころの鹿嵐山ですが、低山でありながら急登でも名をはせています。双耳峰は雌岳730mと雄岳758mと呼ばれ、急峻な登山道はロープが頼りになる。第一登山口に鎮座するお地蔵様は笑みをたたえながら我々を迎えてくれたが、その笑みの理由が雌岳7合目で分かった気がする。「この山を本気で登る気なのか?」とお地蔵様の声がしたような気がした。この急登を50分で登ると、ガイド本に書いてある。「無理だ!」「どんな人がその時間で登れるのだろう?」など雌岳山頂でブツブツ・・・少し下って、少し登ると雄岳山頂だ。これまでの苦労が報われる景色が広がっている。大きな別府湾。雪をかぶった英彦山。遠くに久住山。下山途中に見えた、真っ白な由布岳と鶴見山。万里の長城と言われる絶景ポイントへは、断崖絶壁かと思われる急降下。先頭のまみちゃんが、後輩たちに声をかけている。無事に下山し、お楽しみの安心院ワインと耶馬渓温泉につかり、湯船でよく頑張ったと少し痛むフクラハギを褒めてあげた。皆さんよく頑張りました。
耶馬渓の歴史
新世代第三紀の終わりごろ、九州を南北に分けていた海の底で爆発が始まりました。耶馬溪火山の爆発といわれています。この爆発は、100万年以上も続き、流れ出した大量の溶岩や降り積もった火山灰が海を埋めていき、九州はひとつの島となりました。この爆発で英彦山、犬ケ岳、経読岳、雁股山、大平山と福岡県境の山々ができ、もう一方に中摩殿畑山、一尺八寸山、釣鐘山、樋桶山、桧原山の山々ができました。由布岳、鶴見岳はまだ出来ていなかったので、英彦山から流れ出た川は、土地の低い別府湾の方向に流れていました。
8月11日山の日企画 由布岳東登山道 東峰⇒西峰

由布岳東登山口は、名物の朝霧に覆われていました。山の日だというのに静かな登山口に不安感やら安ど感が混ざった複雑な心境で登山届を記入しました。下見をしていたのでスムーズに登り始めました。本日のメンバーは、先頭が崇ちゃん・9期生の真由美さん・まみちゃん・9期生健ちゃん・佐々木の5名です。しっとりとした空気と静かな樹林帯をゆっくりと登ります。1時間ほど登ると日向岳の分岐に到着。地図で位置を確認して急登と鎖場の登山道を黙々と登ります。途中二か所ほど時間のかかる鎖場がありますが危険はありません。雲の合間に東峰が見えてくると元気が出てきます。最後の急登を上がるとお鉢に出ました。右に進むと西峰へ左に進むと東峰へ出ます。まずは東峰へ。山頂は意外と少ない登山者。こちらの山頂は観光客が多い。昼食を済ませると意外と時間がないのでお鉢を回らずにマタギから西峰をアタック。女性たちをザイルで確保して西峰へ。ここは貸し切りでした。意外と時間を食ってしまったので予定を変更して正面登山口へ下山して、タクシーで東登山口へ移動。その後奥明礬温泉でゆっくりと入浴。別府駅のとり天屋さんでとり天とだご汁を食して帰途に着きました。満足の大名登山でした。
9期生 登山教室2回目 太平山

6月11日(日)平尾台自然の郷登山教室の2回目が開催されました。参加者は5名(一名欠席)と西登会からさっちゃんと崇ちゃんの応援を得ました。(感謝です)梅雨時期の教室なので雨を覚悟の2回目でしたが、早朝に雨は上がって太平山の山頂に着くころには、青空も見られるようになりました。今までの登山教室と違って、男性が一名・女性が五名の参加です。1回目は座学だったので装備を付けて山に入るのは、今回が初めてとなります。真新しいザックや靴を履いて受講生の皆さんが郷へやってきました。11時まで座学を行い、いよいよ初の登山です。吹上峠から望む太平山のすそ野を見て「これを登るんですか----」と・・・初々しいですよね。花や景色を楽しみながら山頂について、山で食べる初めての昼食です。皆さん大満足の様子です。崇ちゃんの粋な計らいで下山コースを変更してキス岩へここでも笑顔と歓声がいっぱいでした。まだ真っ白な受講生を見ているとこのままでいてほしいと願うのは私だけか・・・9期生が少しまとまってきたと感じた2回目の登山教室でした。
6月4日 念願の竜が鼻

昨年からの企画がやっと実現して、7名で竜の背中のごとき急登を無事に終えることができました。猛暑の夏を前に済ませておきたいとの気持ちから、梅雨入り前のこの時期にしてみましたが、晴天で風がなく水分補給を頻繁に行いながらの登山でした。男性4名女性3名の編成は西登会では珍しく男性が多い。それが幸いして危険個所への安全対策としてロープを設置しながらの下山を行うことができました。大きなトラブルは無かったものの下山時にはヒヤリとする場面がありました。登り下りともに2時間を要しました。「また、チャレンジしますか?」の声に全員で「いやーー」と答えるメンバーでした。