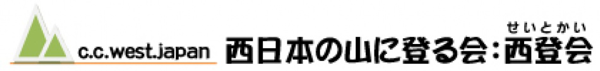地球環境1月号 わたしたちの暮らしと環境 自然と健康を大切にする食育
平成30年1月号 自然にも健康にもやさしい食生活のあり方が、少しずつ見直されています。生産者と消費者双方の安全で安心な食へのアプローチから、新しい時代を賢く生きるための食生活が見えてきます。
1、現代人に対する食育の重要性 食の知識や食を選択する力を獲得し、健康で安全な食生活をおくるための教育「食育」への取り組みが、各地で行われています。2005年の食育基本法成立にあたって、農林水産省がまとめた「我が国の食生活の現状と食育の推進について」では、朝食を抜く子供や、外食・中食が増加していることを裏付けるデータや、食に対する誤った知識の例から、現代人に食育が必要と提言しました。これを受けて、学校や食に関心をもつ人々の自主的な団体、農業・漁業の生産地、食品メーカーが、食育についての取り組みを始めました。食育への取り組みは、全国に広がっています。地域と学校が提携し、子供たちは食の知識を学び、地域に密着した食育を行っています。高齢者の知恵を親子で学び食文化を継承していこうとする、世代をつなぐ食育活動も多くみられます。食育は、偏食、個食、欠食など、現代の食生活に対する見直しの動きといえるでしょう。
2、食育の背景にあるスローフードの考え方 1980年代の半ばに、イタリアで始まったスローフード運動は、その土地の伝統的な食生活や食文化を見つめ直す自然回帰の食のスタイルを提唱する運動です。ファストフードと呼ばれる便利さや安さ、スピードなどを優先し、自然の生態系を崩し、多くの廃棄物を排出し、食の安全や自然とのつながりを断ち切りつつある現代人の食生活とは対極にある動きです。しかし、これらは、必ずしも対立する考えではありません。スローフードは、郷土色などの土地の味、小規模ながら優良な生産者から生まれる味、そして画一的ではない個別の味覚を育てる意識を大切に育てるという考え方であり、食育にもつながります。
3、家庭での食育は食材の安全・安心にこだわる 家庭での食育は、日常の食生活の大切さを啓発すること、旬の食材や地場の食材にこだわった家庭料理を手作りすることから始まります。有機栽培の野菜や無添加の加工食品など、安全・安心を優先に食材を選ぶ視点や、食を通して、子供たちは家庭や地域の人々とのコミュニケーションが大切なことを学びます。他方、朝食をとらない子供、夕食が遅い子供の割合が増え、家庭生活の見直しが迫られています。野菜の摂取不足など若い世代の食生活も大きな課題です。各自が食生活の大切さを考え、食生活の質を充実させましょう。
4、生産者と生活者が手を取り合う 食育を大きな流れにするには、生産者と消費者からの働きかけが必要です。特に重要なのは、生産・流通・販売などの食材の供給側と、生活者の意識改革です。生産者が、手間ひまがかかる有機栽培や無農薬栽培の野菜を作るには、農作物を安定的に購入してくれる消費者がいなければ難しいものです。生産者側には、環境への厳しい取り組みをしている業者に認定マークが与えられ、生活者の側でも、オーガニックフードのように多少価格が高くても安全・安心なものを食べたいという傾向が見えてきました。生産者と生活者がともに自然と健康を大切にする豊かな食生活を追求しています。
参考資料eco検定テキスト 文責:環境社会検定合格者(エコピープル)FUTAMURA
29年8月1日 北部九州豪雨被害状況

九州自然歩道と国立・国定公園内の登山口へのアクセス状況などを巡視してきました。 29年7月20日と21日です。 20日は、日田耶馬英彦山国定公園の状況を見て回りました。彦山川には、流木が大量に流れ込んでいました。家屋に甚大な被害が出ています。まだ復旧工事は本格的には始まっていませんでした。彦山駅から日田へ抜ける道は復旧作業のダンプがひっきりなしに走っていますので、一般車の進入は禁止となっています。従って岳滅鬼山へのアクセスは不可能となっています。犬が岳への野峠登山口は健在です。ただし山中の登山道の確認は行っていませんので入山の際は慎重にお願いします。特に鎖場の通過には特段の配慮をお願いします。鎖の状況を慎重に確認してください。 英彦山系への入山は当分控えたほうが良いと考えます。 さて21日は 阿蘇の状況ですが、こちらも復旧工事の真っ最中と言った感じで、あちらこちらの道路が通行止めとなり、う回路が縦横無尽に走っています。国道57号線から東海大学に抜ける橋はまだできておらず57号線から阿蘇へ向かうことは出来ません。 阿蘇山は噴火のために1km規制中です。従って高岳と中岳への入山はできません。火口に一番近い烏帽子岳と杵島岳・根子岳の入山は可能です。阿蘇付近の道路は地震の影響を受けた状態のままで復旧工事が間に合っていないところも多くありました。 地元の観光業を営む方は、「皆さんに来てほしい。それが一番の応援になる」と言っておられました。 秋ごろに一泊で阿蘇登山の計画を立てようかと思案中です。 私たちの気持ちを被災地に向け続けることが大切なのだと心底思った次第です。 皆さんの応援もよろしくお願いします。
西登会無線クラブ
西登会では現在アマチュア無線免許保有者が9名存在し、無線局を開局しています。
山岳地帯では無線が通信手段として重要であり、今でも年間数件はアマチュア無線で救助されるケースが報告されています。さらに大地震や大型台風などの災害時では、電話の集中による回線のパンク、基地局や中継アンテナの被害によって携帯電話が使用できなくなる可能性が高くなります。
そのようなときの通信手段がアマチュア無線です。
アマチュア無線は行政の防災無線や他の業務無線に比べて、圧倒的に無線局の数も周波数も多いのが特徴です。実際、過去の大震災では一般電話や携帯電話が壊滅状態のなかでアマチュア無線が非常通信手段として大活躍しました。アマチュア無線局と非常通信の協定を結ぶケースも増えてきています。
このように私たち西登会アマチュア無線倶楽部も微力ではありますが、事故や災害時の非常通信において地域社会に貢献できればと考えています。